相続税の申告が必要か、税額がどのくらいになるか知るために、相続税申告上の財産の評価についてお教えします。
相続税の申告が必要か、税額がどのくらいになるか知るために、相続税申告上の財産の評価についてお教えします。

財産の評価方法についてご説明します。
(遺産にかかる相続税と税理士報酬を知りたい方はここをクリック)
土地
不動産は土地と建物に分けて考えます。マンションの敷地は全体の面積(㎡)× 持分割合で計算します。
国税庁がインターネットで、その年分の全国の「路線価」ページを毎年7月に公開しています。道路に㎡当たり単価が千円単位で表示され、土地の面積を乗じると概算評価額になります。
正確には不利な形状等の補正を行いますが、まずは概算で考えます。
路線価(千円) × 面積(㎡) = 評価額(千円)
路線価(千円) × 面積(㎡)
= 評価額(千円)
道路に路線価の付されていない地域は、「倍率地域」となり、「路線価」サイトの別ページに掲載されている「倍率表」の該当地域の倍率を土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を求めます。
固定資産税評価額(円) × 倍率 = 評価額(円)
固定資産税評価額(円)× 倍率
= 評価額(円)
借地権や地主の底地権は、「路線価」ページに記載されている借地権の割合を基に評価します。
評価額(円) × 借地権/底地割合 = 借地権又は底地評価額(円)
評価額(円) × 借地権/底地割合
= 借地権又は底地評価額(円)
貸家が建っている土地の評価は自用の場合の評価額から借家人の権利を控除して評価します。
小規模宅地評価の特例
被相続人が居住用・事業用に使用していた土地については、法定の条件に該当すると、上記の評価額から減額することができます。利用状況により下記の通り、減額割合・対象となる面積に差があります。

小規模宅地の評価の減額は、金額が大きいのでとても重要です。
居住用:
最大330㎡まで80%減額できます。
貸付用:
最大200㎡まで50%減額できます。
貸付でない事業用:
最大400㎡まで80%減額できます。
一定の同族会社に貸付け、法人が貸付以外の事業用に供していた場合:
最大400㎡まで80%減額できます。
(注) 貸付用と他の用途とある場合は、適用できる面積に制限があります。
建物
建物の相続税評価額は相続の年の固定資産税評価額と同じです。
貸している建物の評価額は自用の場合の70%となります。
有価証券
非上場株式を除き、おおよその評価には、相続日に近い時点の証券会社等の評価額で足ります。
非上場株式
法人の決算書・申告書を基に評価しますが、税理士に依頼せずに評価するのは困難です。資産から負債を控除した純資産価格が目安になります。
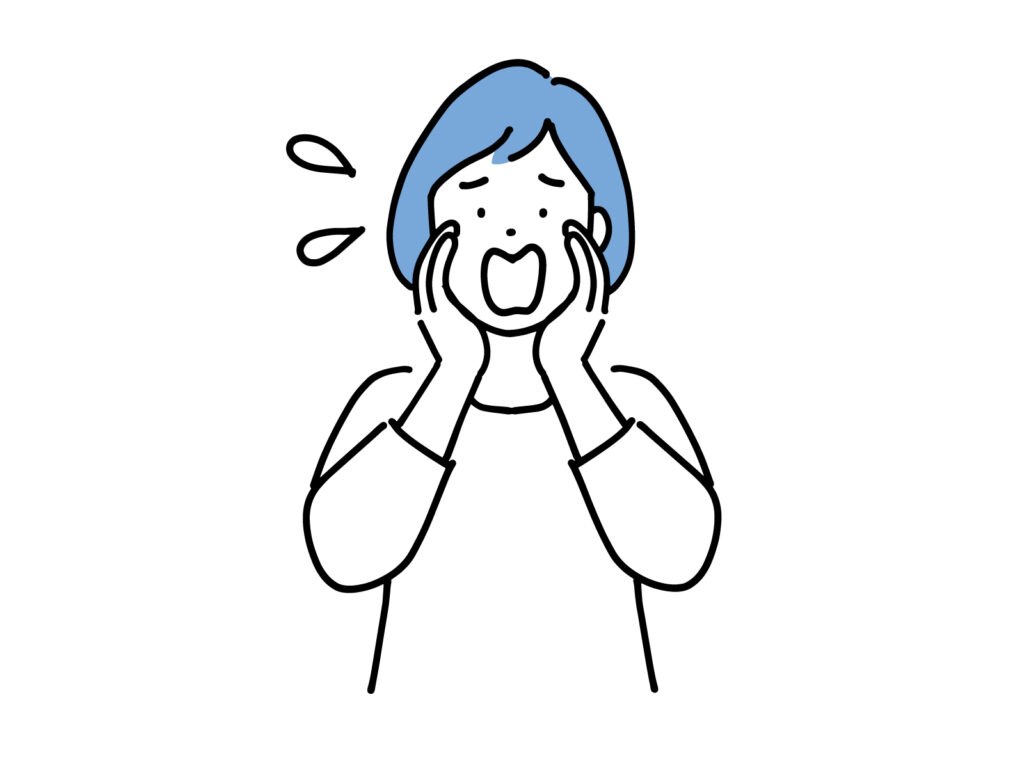
非上場株式の評価は税理士に任せた方がいいですよ。
上場株式
相続日の終値、その月の平均値、前月と前々月の平均値、4つの価格のうち最も安い価格を評価額とします。
投資信託
相続時点の「基準価格」で評価します。解約時に「信託財産留保額」という手数料類似の金額が引かれる銘柄の評価額は、その控除後の金額になります。
社債
相続時点の価格(非上場の場合は発行価格)+ 経過利息(解約した場合の源泉税控除後)で評価します。
現金
相続時点の手許現金等です。入院・葬式費用に充てるために預金口座から引き出して準備しておいた現金も含まれます。
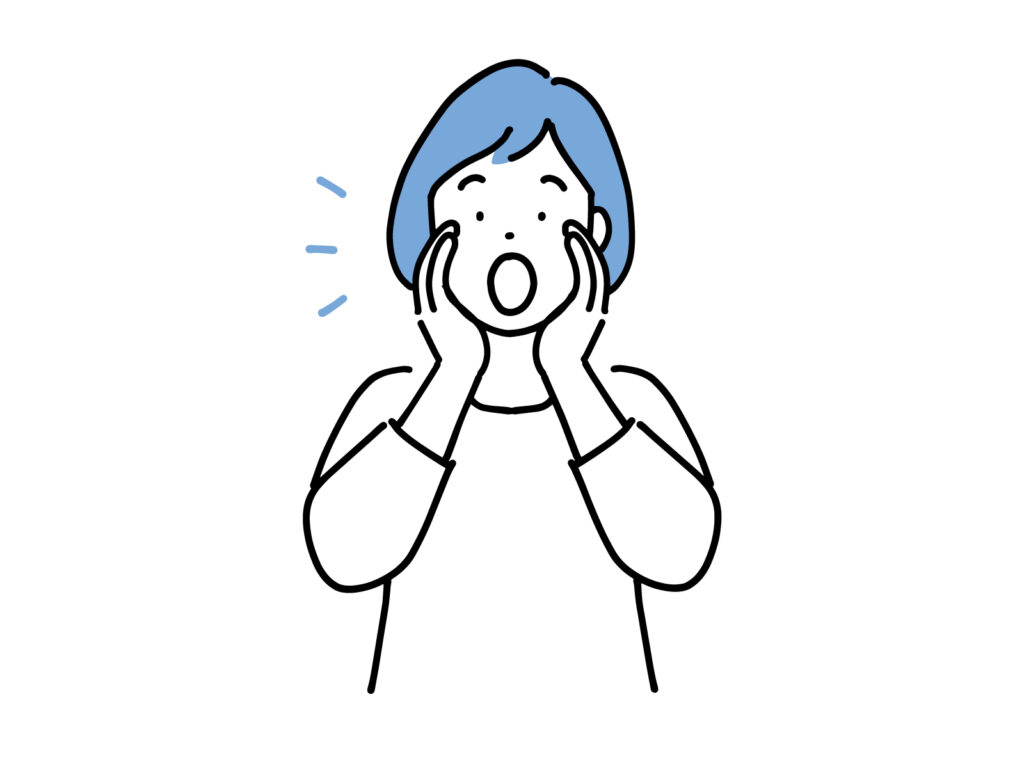
亡くなった方の預金から引き出して相続の時にあった現金は相続財産です。
普通預金
相続時点の残高になります。
定期預金
相続時点の残高になります。解約した場合の源泉税控除後の経過利息を加えます。
生命保険金・退職金
それぞれ、相続人数×500万円の非課税枠が有ります。非課税枠控除後の金額が課税対象となります。
確定拠出企業年金・確定給付企業年金の死亡一時金が退職金と扱われる場合があります。
家庭用財産
特に高価なもの、取得して年数のあまり経過していないものを除き、一括して概算で見積もるのが一般です。
車両
見込売却価格が分かれば見込売却価格、不明な場合には未償却残でも合理性が有ります。
未収金
公租公課の還付金、高額医療の給付金などが有ります。
保険金に関する権利
契約者・保険料の負担者が被相続人で、被保険者が親族等の保険契約は被相続人の財産とされます。評価額は、相続時点で解約した場合の返戻金になり、保険会社に照会します。
貴金属・書画・骨董
相続時点の価格です。高価なものは鑑定依頼が必要になる場合もあります。
以上が主な財産になります。相続税申告が必要かどうか、相続税の概算額を知るためには、以上のような計算で足りると思われます。
お問合せ
以下の個人情報は、ご記入内容の検討と記入者ご本人への連絡のためのみに利用します。
また、他に開示することはございません。
275-0014
千葉県習志野市鷺沼2-9-50-212
小林禧継税理士事務所
Tel. 090-6075-2437 E-mail: yxiaolin117@gmail.com

コメントを残す